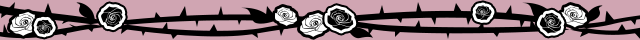
義娘のつぼみ〜背徳の誘い〜
第1章 プロローグ
彼は悲しみに暮れていた。
寝室でベッドの端に腰掛け、部屋の明かりも点けずに、もう何時間も。
涙はとうに流し尽くしてしまったのか、不思議とこぼれ落ちることはなかった。
扉の向こうから足音が近づいてくる。けれども彼は全く意に介さない。
足音が扉の前で止まり、ノックが三回聞こえた。しかし、今の彼にはそれに応える気力すらなかった。
しばしの静寂が続いた。
やがて、足音の主はゆっくりと、その扉を開いた。外から眩しい明かりが差し込む。彼は思わず目を細めた。
「わたし決めた。わたしがパパの奥さんになる」
部屋に入るなり、足音の主は言った。彼の目の前にはひとりの少女が立っていた。
突然の、彼女の宣言とも取れる言葉に、楠本武司(くすもとたけし)は驚愕し、そして困惑する。
例えば、幼少期の女児が自分の父親に向かって「パパのお嫁さんになる」と言うのは、よく聞く微笑ましいエピソードである。だが、今彼の目の前にいるのは中学一年生の、十三歳の少女である。普通であれば、冗談でもそんなことは言わない年頃のはずだ。近年では父親をウザい存在、不潔な存在として敬遠するのが多数派だろう。
しかし彼女は本気だった。心の底から、今現在の彼女自身の本心を口にしていた。
「――ありがとう茉由。とてもうれしいよ」
そうか、彼女は自分を励まそうと、懸命になっているのだ。いつまでも塞ぎ込んでいる場合ではない――そう考えた武司は、ようやく口を開いた。
設楽茉由(したらまゆ)、少女の名前だ。戸籍の上では武司の娘ではあるのだが、理由(わけ)あって別姓を名乗っている。『設楽』は武司の妻の名字だ。
法律上では、彼女は紛れもない武司の娘である。だが、血の繋がりはない。武司にとって、茉由は本当の子供ではないからだ。仮に、この先ふたりが本当に結婚したとしても、血縁的な近親婚にはならない。
「あと何年かして、茉由がもっと大人になったら、そうしたら結婚しよう」
長く悲しみに暮れていた武司は、微(かす)かではあるが、ようやく笑顔を取り戻すことができた気がした。ところがその直後、彼の表情はふたたび困惑へと変わることになる。
「わたし、もう子供じゃない。大人だもん」
そう言いながら、茉由は部屋の照明のスイッチを入れる。室内に白い光が広がった。
寝室でベッドの端に腰掛け、部屋の明かりも点けずに、もう何時間も。
涙はとうに流し尽くしてしまったのか、不思議とこぼれ落ちることはなかった。
扉の向こうから足音が近づいてくる。けれども彼は全く意に介さない。
足音が扉の前で止まり、ノックが三回聞こえた。しかし、今の彼にはそれに応える気力すらなかった。
しばしの静寂が続いた。
やがて、足音の主はゆっくりと、その扉を開いた。外から眩しい明かりが差し込む。彼は思わず目を細めた。
「わたし決めた。わたしがパパの奥さんになる」
部屋に入るなり、足音の主は言った。彼の目の前にはひとりの少女が立っていた。
突然の、彼女の宣言とも取れる言葉に、楠本武司(くすもとたけし)は驚愕し、そして困惑する。
例えば、幼少期の女児が自分の父親に向かって「パパのお嫁さんになる」と言うのは、よく聞く微笑ましいエピソードである。だが、今彼の目の前にいるのは中学一年生の、十三歳の少女である。普通であれば、冗談でもそんなことは言わない年頃のはずだ。近年では父親をウザい存在、不潔な存在として敬遠するのが多数派だろう。
しかし彼女は本気だった。心の底から、今現在の彼女自身の本心を口にしていた。
「――ありがとう茉由。とてもうれしいよ」
そうか、彼女は自分を励まそうと、懸命になっているのだ。いつまでも塞ぎ込んでいる場合ではない――そう考えた武司は、ようやく口を開いた。
設楽茉由(したらまゆ)、少女の名前だ。戸籍の上では武司の娘ではあるのだが、理由(わけ)あって別姓を名乗っている。『設楽』は武司の妻の名字だ。
法律上では、彼女は紛れもない武司の娘である。だが、血の繋がりはない。武司にとって、茉由は本当の子供ではないからだ。仮に、この先ふたりが本当に結婚したとしても、血縁的な近親婚にはならない。
「あと何年かして、茉由がもっと大人になったら、そうしたら結婚しよう」
長く悲しみに暮れていた武司は、微(かす)かではあるが、ようやく笑顔を取り戻すことができた気がした。ところがその直後、彼の表情はふたたび困惑へと変わることになる。
「わたし、もう子供じゃない。大人だもん」
そう言いながら、茉由は部屋の照明のスイッチを入れる。室内に白い光が広がった。
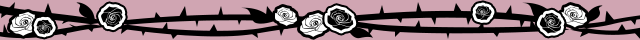
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える