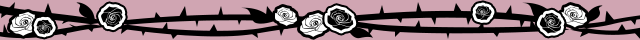
義娘のつぼみ〜背徳の誘い〜
第3章 親子の性教育
2
茉由はバスルームで身体を洗っていた。
この後しばらくしたら、彼女は両親の寝室で二人のセックスを見学する。大人の男と女が子供を作るための行為を、目の当たりにするのだ。
もちろん理屈では知っていた。だが、学校で教わったのは図やイラストばかりで、実感に乏しいのも事実だった。雑誌の記事も同様だ。
両親の、見てはいけない部分を目にする後ろめたさは確かにある。だが、それ以上に、今の茉由にとっては性への関心の方が遥かに上回っていた。
学校ではクラスメイトも含め、相当数の女子がすでに初体験を済ませているという。中でも早い子は、小学校の中・高学年のころに処女を捨てたそうだ。相手はかなり年上の高校生や大学生だったり、あるいは同じ中学校の男子だったり、中には教師と関係を持っている女子もいると、噂を耳にしていた。
また、SNSを利用して、金銭目的の援助交際で見知らぬ相手とセックスをするのも、茉由たちの世代ではもはや当たり前のことだった。何度か茉由も誘われたことはあったが、その時は勇気がなくて断った。いや、勇気がなかったわけではない。初めてセックスする相手、処女を捧げる相手は、どこの誰でもいいとは思えなかったのである。
自分がこれからその行為をするわけでもないというのに、茉由は普段以上に念入りに身体を洗った。夫婦に混ざって自分もエッチな経験が出来るのではないか、心の何処かでそんな期待があったのかもしれない。武司になら、血の繋がらない父親の彼になら、処女(ヴァージン)をあげてもいいと、彼女は思っていた。
(――まさか)
直後、茉由は自分の考えを否定する。
(そんなことしたら、ママを悲しませちゃう)
彼女は温めのシャワーを浴びて、頭と火照った身体を冷ました。
バスルームを出て身体を拭き、用意された下着とパジャマ代わりのTシャツ・短パンを身に着ける。ドライヤーで長い髪を乾かし、ヘアゴムで束ねた。
時間は間もなく午後十時を指そうとしていた。すでに入浴を済ませた両親は、今ごろ寝室で自分のことを待っているだろう。茉由は次第に胸の鼓動が高鳴るのを覚えていた。
茉由はバスルームで身体を洗っていた。
この後しばらくしたら、彼女は両親の寝室で二人のセックスを見学する。大人の男と女が子供を作るための行為を、目の当たりにするのだ。
もちろん理屈では知っていた。だが、学校で教わったのは図やイラストばかりで、実感に乏しいのも事実だった。雑誌の記事も同様だ。
両親の、見てはいけない部分を目にする後ろめたさは確かにある。だが、それ以上に、今の茉由にとっては性への関心の方が遥かに上回っていた。
学校ではクラスメイトも含め、相当数の女子がすでに初体験を済ませているという。中でも早い子は、小学校の中・高学年のころに処女を捨てたそうだ。相手はかなり年上の高校生や大学生だったり、あるいは同じ中学校の男子だったり、中には教師と関係を持っている女子もいると、噂を耳にしていた。
また、SNSを利用して、金銭目的の援助交際で見知らぬ相手とセックスをするのも、茉由たちの世代ではもはや当たり前のことだった。何度か茉由も誘われたことはあったが、その時は勇気がなくて断った。いや、勇気がなかったわけではない。初めてセックスする相手、処女を捧げる相手は、どこの誰でもいいとは思えなかったのである。
自分がこれからその行為をするわけでもないというのに、茉由は普段以上に念入りに身体を洗った。夫婦に混ざって自分もエッチな経験が出来るのではないか、心の何処かでそんな期待があったのかもしれない。武司になら、血の繋がらない父親の彼になら、処女(ヴァージン)をあげてもいいと、彼女は思っていた。
(――まさか)
直後、茉由は自分の考えを否定する。
(そんなことしたら、ママを悲しませちゃう)
彼女は温めのシャワーを浴びて、頭と火照った身体を冷ました。
バスルームを出て身体を拭き、用意された下着とパジャマ代わりのTシャツ・短パンを身に着ける。ドライヤーで長い髪を乾かし、ヘアゴムで束ねた。
時間は間もなく午後十時を指そうとしていた。すでに入浴を済ませた両親は、今ごろ寝室で自分のことを待っているだろう。茉由は次第に胸の鼓動が高鳴るのを覚えていた。
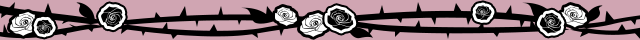
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える