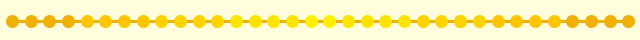
リーニエント
第3章 リンデンビバーナム
ほの暗い、此処は旧校舎の中。
先刻までいた草が覆い茂る外とは違い、肌寒さに身震いした。
埃まみれの机上に座る彼女の前には、友哉が割るように膝の間に立つ。
「あ、あの……やっぱり…っんん」
「は…っ、も……遅い」
「っふ……んう」
不安げに見つめる莢花の唇を塞ぐと、二度三度と角度を変えながら啄み、吸い上げる。
「はあはっ……やだっやあーっふぇ…っく」
「そこ……泣くとこじゃないでしょ」
「だっ……て、ひぅっ」
頬をすり合わせるように密着すると、彼女の耳元へ息を吐く。
意識が違う方向へ飛んだらしく、泣きやむ莢花。
再び重なる唇は先刻よりも熱く感じる。
その間も友哉の手は開襟シャツのボタンを淡々と外していった。
「何?その手、退けてくれないかな。すっごく邪魔」
「だって!だって、キスだけ……って」
「お前さ……、何か勘違いしてない?オレ達のあれは中断したの。キスだけで終るわけないでしょ」
「……え」
「誰かさんが覗きさえしてなければね。オレは今頃、アイツとこうしてたって、事」
「きゃっ!?」
突然担がれ、すぐに床へ転がされると上がる悲鳴。
更に白く舞う砂埃が、目と喉を攻撃してくるのだった。
「ケホケホッ…!あのっ…あっ友哉……くん?」
「オレねえ、結構怒ってんの……ストーカーのあんたなら解るよね?」
「私、ストーカーじゃ、ないっっ」
目の痛みと、咳の二重苦。
そしてこの不穏な空気。
莢花は本能的に感じた恐怖から、逃げなければと焦っていた。
「でも、好きだからしたんだよね?ストーキング」
「そ、れは」
莢花本人の気持ちでは、そんな黒い話では無かった。
ただ好きな彼を見付けて、追いかけただけ。
ただの好奇心である。
パニックからか立ち上がることが叶わず、ズルズルと這いずるように友哉から離れる。
「ああ、逃げないでよ」
「やっ……離して!」
だがそんな事許すはずもなく、彼女の上へ覆い被さった。
「だからさ、脅迫した責任。とらないと、ね?」
弧を描いた口許に、射るような瞳のその顔はまるで悪魔。
いったいどちらが脅迫を受けているのか。
後悔と絶望に莢花の喉がヒュッと一度、虚しく鳴った。
END
20251217
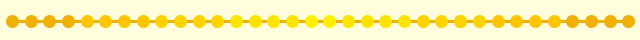
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える