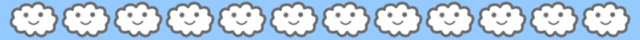
ライフ オブ ザ マウンテン
第2章 3
何度か家を追い出されていると、隣人の年老いたおばあさん、マーサ・レティスが僕に声をかけてくれた。「どうしたんだい?時々、家の前に座っているけど、どうして家に入らないのかね?」僕は下を向いて何分間か黙っていた。マーサは自分の家に戻っていったが、すぐに戻ってきて、お菓子を私にもってきてくれた。僕は人に優しくされたのが初めてだったからそれを嬉しく思い、マーサに感謝した。しかし、それを遠目で見ていた母は憤慨し、物凄い剣幕で僕達に近づきマーサを口煩く罵った。「こんな子にそんなものあげるんじゃないよ老いぼれ。こいつは不幸がお似合いなのさ。なんたってこの貧困区に産まれた哀れな男の子なんだからね」マーサは反論したが、母の事だ、もちろんまともに取り合わず、早々に家に帰した。そして僕を家に入れ、説教を二時間もした。「あんたは私と旦那だけのものよ。といっても奴隷だけど。だから他の連中と関わるんじゃない、分かったね?」渋々うなずいたが、その日はいつもの日常と違って幸せな気分を味わったような気がした。毎日、罵られたり暴力を振るわれ
るのは、時が経つにつれ、厭でも慣れていくものだ。それに耐えられたのは近々、学校に行く事が分かったからだ。学校に行けばマーサのような優しい人と出会る機会があるだろう、そう思うと一筋の光が暗い洞窟に差し込んだような気分になった。でもそれは儚い、馬鹿げた望みだったのだ。両親は学校に行く事を許さなかったから。学校に行く歳になっても私は家庭の為に働いた。洗濯物を洗って干したり、食事を作ったり、(不味かったら暴力を振るわれた)掃除をしたり、買い物をしたり。それでも、いくらやった所で感謝すらされないのは当然のごとくといった感じで、感謝よりも罵るのがこの家族の伝統的な慣わしなのだろう、それを僕は理解し、やるのが当たり前と思い一生懸命努めた。地元の学校の終了時間になると、当時僕と同じぐらいの年の子供が帰り道で僕の家を通るのだが、それを見るのは辛かった。皆と同じことが出来ない、自分は何て無力なのだろう、これから先、あの二人とずっと関わっていって何があるのか…考えただけでも気が滅入る。言い忘れていたが、この家には隠れたルールがある。その一つは父の尻を叩くこと。彼が異常なサドマゾな
のは薄々気づいていたが、一般の人からしたら異常、特に異常であっただろう。
るのは、時が経つにつれ、厭でも慣れていくものだ。それに耐えられたのは近々、学校に行く事が分かったからだ。学校に行けばマーサのような優しい人と出会る機会があるだろう、そう思うと一筋の光が暗い洞窟に差し込んだような気分になった。でもそれは儚い、馬鹿げた望みだったのだ。両親は学校に行く事を許さなかったから。学校に行く歳になっても私は家庭の為に働いた。洗濯物を洗って干したり、食事を作ったり、(不味かったら暴力を振るわれた)掃除をしたり、買い物をしたり。それでも、いくらやった所で感謝すらされないのは当然のごとくといった感じで、感謝よりも罵るのがこの家族の伝統的な慣わしなのだろう、それを僕は理解し、やるのが当たり前と思い一生懸命努めた。地元の学校の終了時間になると、当時僕と同じぐらいの年の子供が帰り道で僕の家を通るのだが、それを見るのは辛かった。皆と同じことが出来ない、自分は何て無力なのだろう、これから先、あの二人とずっと関わっていって何があるのか…考えただけでも気が滅入る。言い忘れていたが、この家には隠れたルールがある。その一つは父の尻を叩くこと。彼が異常なサドマゾな
のは薄々気づいていたが、一般の人からしたら異常、特に異常であっただろう。
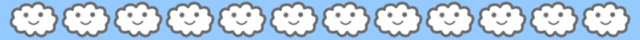
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える