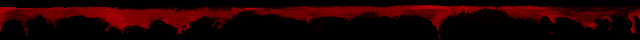
庭師-ブラック・ガーデナー-
第2章 1
五人分のインタビューを終えた日、担当編集者の小野塚さんから電話がかかってきた。彼女は言いにくそうに、「話をしたい」とだけ言い、半ば強引に場所と時間を指定してきた。それでも私はまだ事の次第が予想できず、インタビューの人選に変更でもあったのかしらと呑気なことを考えながら、待ち合わせ場所の喫茶店にのこのこと出かけて行った。
人選の変更は、インタビューではなく、インタビュアーのほうだった。つまり、私は切られてしまったのだ。
小野塚さんが回りくどい言い方で述べたところによれば、共同執筆者である先輩ライターが、私の書いた文章を良く思わなかったらしい。この程度の取材力、文章力で共同執筆などとんでもない、この人を降ろさなければ私が降りる、という剣幕だったそうだ。
「私は悪くないと思うのよ、寺内さんの文章。ただ、あっちのセンセイがね……何が気に入らないのか知らないけど、ヘソを曲げちゃうと難しい人でね……」
そういう風に言えば、私が傷つかずにすむとでも思っているようだった。自分の責任を回避して、「あっちのセンセイ」に押しつけているだけなのに。
ともかく小野塚さんはしきりに恐縮し、「書いてもらった分のギャラは払うわ」と繰り返した。あなたの書いた原稿は使えないが、手間賃だけは払う、ということだ。
私は何と答えたのだろう。なんだか靄がかかったように、記憶がはっきりしない。逆上したり、怒鳴ったり、泣いたりという態度は取らなかったことだけは確かだ。
自制心があったわけではない。そんな激しい反応ができるほど、頭かな回転してなかったのだ。「はあ」とか「まあ」とか曖昧なことを言いながら、そそくさと席を立って、逃げるように店を出た気がする。
それから数日間、落ち込んだまま家でごろごろしていた。この仕事のために、定期的に入れていた雑誌の仕事を断ってしまったので、することがなかった。
私はしばらくぶりに浩一のことを思い出したが、電話をしてもずっと留守電になっていた。メッセージを吹き込んでも、かかってこなかった。私は彼のマンションを訪ねた。ドアを開けた彼は、滑稽なほど慌てふためいていた。足元を見たら、ほっそりと可愛らしい女性の靴がそろえてあった。
人選の変更は、インタビューではなく、インタビュアーのほうだった。つまり、私は切られてしまったのだ。
小野塚さんが回りくどい言い方で述べたところによれば、共同執筆者である先輩ライターが、私の書いた文章を良く思わなかったらしい。この程度の取材力、文章力で共同執筆などとんでもない、この人を降ろさなければ私が降りる、という剣幕だったそうだ。
「私は悪くないと思うのよ、寺内さんの文章。ただ、あっちのセンセイがね……何が気に入らないのか知らないけど、ヘソを曲げちゃうと難しい人でね……」
そういう風に言えば、私が傷つかずにすむとでも思っているようだった。自分の責任を回避して、「あっちのセンセイ」に押しつけているだけなのに。
ともかく小野塚さんはしきりに恐縮し、「書いてもらった分のギャラは払うわ」と繰り返した。あなたの書いた原稿は使えないが、手間賃だけは払う、ということだ。
私は何と答えたのだろう。なんだか靄がかかったように、記憶がはっきりしない。逆上したり、怒鳴ったり、泣いたりという態度は取らなかったことだけは確かだ。
自制心があったわけではない。そんな激しい反応ができるほど、頭かな回転してなかったのだ。「はあ」とか「まあ」とか曖昧なことを言いながら、そそくさと席を立って、逃げるように店を出た気がする。
それから数日間、落ち込んだまま家でごろごろしていた。この仕事のために、定期的に入れていた雑誌の仕事を断ってしまったので、することがなかった。
私はしばらくぶりに浩一のことを思い出したが、電話をしてもずっと留守電になっていた。メッセージを吹き込んでも、かかってこなかった。私は彼のマンションを訪ねた。ドアを開けた彼は、滑稽なほど慌てふためいていた。足元を見たら、ほっそりと可愛らしい女性の靴がそろえてあった。
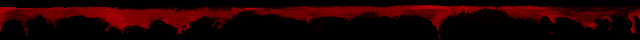
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える