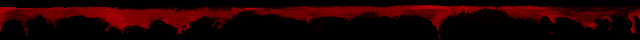
庭師-ブラック・ガーデナー-
第2章 1
悶々としながら、でも打開の道が見つからなくて、締め切りに追われながら提灯持ちみたいな記事ばかり書き続けていたある日、突然、夢のような話が転がりこんできた。
以前からよく世話になっていた編集者に、本を書かないかと言われたのだ。いろいろな業界で活躍している三十代の女性へのインタビューをまとめるという企画本で、インタビュアーとして私の名前も出る。章末ごとにコラムのページを設け、そこには私が自由に文章を書く、というものだった。
ただし、私だけの仕事ではない。もう一人、先輩格のライターがいて、共同執筆という形にする。名前の扱いはもちろんその人がメイン、という条件だった。
文句のあるはずがない。私は大喜びでこの話に飛びついた。「寺内さやか」という名前が表紙に印刷された本が、全国の書店に並ぶのだ。その光景を想像しただけで心がはずんだ。
浩一と二人で、ちょっと値段の張るレストランで祝杯を上げた。私の奢りで、だ。浩一は、あんまり飲めないくせにこの日ばかりはワインを付き合ってくれた。
忙しい日々が始まった。企画書に従って、私は何人かの女性に会い、話を聞いた。独立して会社を作った人、三十歳から司法試験の勉強を始め弁護士になった人、趣味の編み物を極めて教室を開いた人、などなど。みな自信にあふれていて、話が面白く、魅力的だった。女も三十代になるとカオじゃなく内面よね、などと陳腐な感慨を抱いてしまうくらい、どの人も美しく見えた。
やりがいのある仕事に打ち込んでいる人は、こんなにもキラキラしているものなのだ。私は彼たちの話を聞いているうちに、いつのまにか逆に自分がインタビューを受けているような錯覚を抱くこともあった。
錯覚。そう。私は彼女たちの輝きを分けてもらったわけではなく、その光のまぶしさに目がくらんで、浮かれているだけだったのだ。
取材と執筆は順調に進んだ。ワープロのキーを一つ叩くのにも、これまでになく力が入った。表現に頭を悩ませたり、辞典をひっくり返したり、ライターになりたての頃みたいな興奮を感じながら、私は記事をまとめた。浩一からしばしばかかってくる電話が、鬱陶しく感じられた。デートの約束を何度かすっぽかした。浩一がちっとも怒らないのが妙な感じだったけれど、私は仕事のことで頭がいっぱいだった。
以前からよく世話になっていた編集者に、本を書かないかと言われたのだ。いろいろな業界で活躍している三十代の女性へのインタビューをまとめるという企画本で、インタビュアーとして私の名前も出る。章末ごとにコラムのページを設け、そこには私が自由に文章を書く、というものだった。
ただし、私だけの仕事ではない。もう一人、先輩格のライターがいて、共同執筆という形にする。名前の扱いはもちろんその人がメイン、という条件だった。
文句のあるはずがない。私は大喜びでこの話に飛びついた。「寺内さやか」という名前が表紙に印刷された本が、全国の書店に並ぶのだ。その光景を想像しただけで心がはずんだ。
浩一と二人で、ちょっと値段の張るレストランで祝杯を上げた。私の奢りで、だ。浩一は、あんまり飲めないくせにこの日ばかりはワインを付き合ってくれた。
忙しい日々が始まった。企画書に従って、私は何人かの女性に会い、話を聞いた。独立して会社を作った人、三十歳から司法試験の勉強を始め弁護士になった人、趣味の編み物を極めて教室を開いた人、などなど。みな自信にあふれていて、話が面白く、魅力的だった。女も三十代になるとカオじゃなく内面よね、などと陳腐な感慨を抱いてしまうくらい、どの人も美しく見えた。
やりがいのある仕事に打ち込んでいる人は、こんなにもキラキラしているものなのだ。私は彼たちの話を聞いているうちに、いつのまにか逆に自分がインタビューを受けているような錯覚を抱くこともあった。
錯覚。そう。私は彼女たちの輝きを分けてもらったわけではなく、その光のまぶしさに目がくらんで、浮かれているだけだったのだ。
取材と執筆は順調に進んだ。ワープロのキーを一つ叩くのにも、これまでになく力が入った。表現に頭を悩ませたり、辞典をひっくり返したり、ライターになりたての頃みたいな興奮を感じながら、私は記事をまとめた。浩一からしばしばかかってくる電話が、鬱陶しく感じられた。デートの約束を何度かすっぽかした。浩一がちっとも怒らないのが妙な感じだったけれど、私は仕事のことで頭がいっぱいだった。
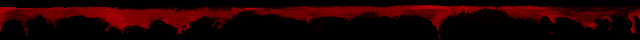
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える