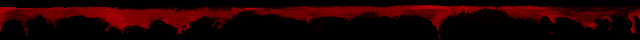
庭師-ブラック・ガーデナー-
第2章 1
ぐるっと一周して元に戻っただけだ。私はぼんやりそう考え、「今までありがとう」と自分でも驚くぐらい静かな声で言って受話器を置いた。当時私が住んでいたアパートには、浩一の歯ブラシやらシェーバーやらがごっそり置いてあったので、まとめて箱に詰め、宅配便で送った(ささやかな腹いせに、着払いにした)。
間もなく、銀行口座に原稿料が振り込まれた。五万円に満たない金額だった。
支払通知書の数字を眺めているうちに、私は初めて怒りを感じた。指先が震えるほど、激しい怒りだった。金額が少なかったからではない。使えもしない原稿に、申し訳程度の代価が支払われたことが情けなかった。出版社よりも、実力のない自分に腹が立ってならなかった。
まだ昼だったが、近所の酒屋でウィスキーを買ってきて、部屋で一人で飲み始めた。酔いが回るにつれて、インタビューをした五人の女性たちの顔が次々に思い浮かんだ。みんなきれいにお化粧して、いいスーツを着て、ブランド品のバッグを持って、背筋をピンと伸ばして、自信に満ちた態度で話をした。私とあまり年齢が違わないのに、周囲から認められて、地位と収入を手にした人たちばかり。仕事一筋の人もいたし、結婚して子供のいる人もいたが、みんなそれぞれに幸せそうだった。彼女たちのまぶしさに当てられ、浮かれているうちに、私はあっさり仕事と男と両方失ってしまったのだ。悲しいというか、腹立たしいというか、情けないというか、恥ずかしいというか、飲んでいるうちに涙が止まらなくなって、泣きながらストレートのウィスキーを胃に流し込んだ。
ヤケ酒なんて初めてだ。私は学生時代からお酒が好きだが、飲む時は楽しく、がモットーだった。飲みながら浩一に愚痴ってる時ですら、次から次へ威勢よく罵詈雑言を並べて、笑い転げたりした。まさか自分が、一人でべそべそ泣きながら部屋でウィスキーをあおるようなみっともない女になるとは思わなかった。
ボトル半分ぐらい、一人であけてしまった。次の日は当然、二日酔いだった。昼近くになってふらふらしながら起き出し、朝刊を開くと、折り込みの広告がばさっと足元に落ちた。
私は屈み込んでチラシの束を拾い上げ、ゴミ箱に突っ込もうとして、ふと手を止めた。
間もなく、銀行口座に原稿料が振り込まれた。五万円に満たない金額だった。
支払通知書の数字を眺めているうちに、私は初めて怒りを感じた。指先が震えるほど、激しい怒りだった。金額が少なかったからではない。使えもしない原稿に、申し訳程度の代価が支払われたことが情けなかった。出版社よりも、実力のない自分に腹が立ってならなかった。
まだ昼だったが、近所の酒屋でウィスキーを買ってきて、部屋で一人で飲み始めた。酔いが回るにつれて、インタビューをした五人の女性たちの顔が次々に思い浮かんだ。みんなきれいにお化粧して、いいスーツを着て、ブランド品のバッグを持って、背筋をピンと伸ばして、自信に満ちた態度で話をした。私とあまり年齢が違わないのに、周囲から認められて、地位と収入を手にした人たちばかり。仕事一筋の人もいたし、結婚して子供のいる人もいたが、みんなそれぞれに幸せそうだった。彼女たちのまぶしさに当てられ、浮かれているうちに、私はあっさり仕事と男と両方失ってしまったのだ。悲しいというか、腹立たしいというか、情けないというか、恥ずかしいというか、飲んでいるうちに涙が止まらなくなって、泣きながらストレートのウィスキーを胃に流し込んだ。
ヤケ酒なんて初めてだ。私は学生時代からお酒が好きだが、飲む時は楽しく、がモットーだった。飲みながら浩一に愚痴ってる時ですら、次から次へ威勢よく罵詈雑言を並べて、笑い転げたりした。まさか自分が、一人でべそべそ泣きながら部屋でウィスキーをあおるようなみっともない女になるとは思わなかった。
ボトル半分ぐらい、一人であけてしまった。次の日は当然、二日酔いだった。昼近くになってふらふらしながら起き出し、朝刊を開くと、折り込みの広告がばさっと足元に落ちた。
私は屈み込んでチラシの束を拾い上げ、ゴミ箱に突っ込もうとして、ふと手を止めた。
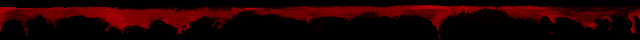
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える