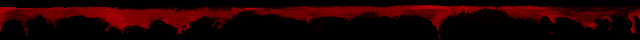
庭師-ブラック・ガーデナー-
第2章 1
どうせなら、もっと役に立ちそうなコーヒー詰め合わせとかカレーのレトルトパックとかを贈って欲しかったんん
とにかくパキラに水をやり、リビングの隅に置いて、本の整理を続けた。配置を考えたり、ついパラパラと読みふけってしまったりで、はかどらない。雑誌のバックナンバーを読み始めたら止まらなくなって、はっと気がついたらお昼をすぎていた。
冷蔵庫の中には卵と牛乳とビールぐらいしか入ってない。確か、近所にファミレスがあったはずだ。エレベーターで階下に下り、外に出たときだった。きゅんきゅんと、あわれっぽい声がした。
子犬だ。マンションの花壇を仕切っている鉄柵に、網でつながれている。確か、ミニチュアダックスフントとかいう種類だ。小さくて、足が短くて、愛敬のある身体つきをしている。汗ばむほどの陽気だというのに、ぽてっとした身体に窮屈そうな赤い毛糸のベストを着せられていた。
かたわらに幼い女の子が立っていた。四、五歳ぐらいだろうか。手に持ったおもちゃのスコップで、リズムをつけて犬の頭を叩いている。犬が身をよじって鳴くのを面白がっている様子だった。
最初は、じゃれているのかと思ったが、それにしては叩き方が乱暴だった。スコップの尖った先で、犬の鼻先を突いたりしている。犬は本気で嫌がっていた。子供の悪戯で済ますには悪質だ。
私は立ち止まり、あたりを見回した。犬の飼い主も、女の子の親も近くにいないようだ。
「やめなさい」
声をかけると、女の子は手を止めてこちらを見上げた。
髪を二つに結って、赤いボンボンのついたゴムで止めている。目のくりっとした、愛らしい顔立ちだった。何を言われたか理解していないような、きょとんてした顔で私を見上げていた。
「わんちゃん、かわいそうでしょう。ほら、痛い痛いって言ってるよ」
私は身をかがめて、なるべく優しい大人の声を出してみた。子供は苦手だ。
子供は目を眇め、鼻のあたりに皺を寄せた。突然、私を「敵」と認識したらしい。こんなに小さいくせに、悪意の見せ方だけは一人前だ。
方針変更。優しいお姉さん路線はやめて、怖いおばさんになることにした。腕を組み、睨みつけると、子供はたじろいだ様子もなく「うるせえ、バカ」と言った。
なんという可愛げのなさ。
とにかくパキラに水をやり、リビングの隅に置いて、本の整理を続けた。配置を考えたり、ついパラパラと読みふけってしまったりで、はかどらない。雑誌のバックナンバーを読み始めたら止まらなくなって、はっと気がついたらお昼をすぎていた。
冷蔵庫の中には卵と牛乳とビールぐらいしか入ってない。確か、近所にファミレスがあったはずだ。エレベーターで階下に下り、外に出たときだった。きゅんきゅんと、あわれっぽい声がした。
子犬だ。マンションの花壇を仕切っている鉄柵に、網でつながれている。確か、ミニチュアダックスフントとかいう種類だ。小さくて、足が短くて、愛敬のある身体つきをしている。汗ばむほどの陽気だというのに、ぽてっとした身体に窮屈そうな赤い毛糸のベストを着せられていた。
かたわらに幼い女の子が立っていた。四、五歳ぐらいだろうか。手に持ったおもちゃのスコップで、リズムをつけて犬の頭を叩いている。犬が身をよじって鳴くのを面白がっている様子だった。
最初は、じゃれているのかと思ったが、それにしては叩き方が乱暴だった。スコップの尖った先で、犬の鼻先を突いたりしている。犬は本気で嫌がっていた。子供の悪戯で済ますには悪質だ。
私は立ち止まり、あたりを見回した。犬の飼い主も、女の子の親も近くにいないようだ。
「やめなさい」
声をかけると、女の子は手を止めてこちらを見上げた。
髪を二つに結って、赤いボンボンのついたゴムで止めている。目のくりっとした、愛らしい顔立ちだった。何を言われたか理解していないような、きょとんてした顔で私を見上げていた。
「わんちゃん、かわいそうでしょう。ほら、痛い痛いって言ってるよ」
私は身をかがめて、なるべく優しい大人の声を出してみた。子供は苦手だ。
子供は目を眇め、鼻のあたりに皺を寄せた。突然、私を「敵」と認識したらしい。こんなに小さいくせに、悪意の見せ方だけは一人前だ。
方針変更。優しいお姉さん路線はやめて、怖いおばさんになることにした。腕を組み、睨みつけると、子供はたじろいだ様子もなく「うるせえ、バカ」と言った。
なんという可愛げのなさ。
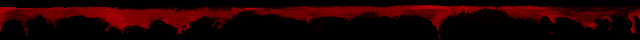
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える