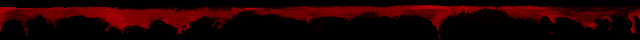
庭師-ブラック・ガーデナー-
第2章 1
「外では悪いことしてるくせに、親の前ではいい子ぶってるんですよ。最近の親は甘いから、自分ちの子が何をしているか全然知らないんです。一度注意したんですけど、かえって嫌な顔をされるばっかりでねえ。難癖をつけたと思われたみたい。同じマンションでもめるのはイヤだから、それ以来、かかわらないようにしてるんですけどね。ああいう子が将来どういうことになるか……」
野末さんは話好きらしく、まだいろいれら語りたそうだったが、私は適当に切り上げた。引っ越し早々、住人のトラブルに巻き込まれたくはない。
最上階の林原さんには要注意、と心のメモに書き留めておくことにした。
☆
一週間経っても、部屋の中のダンボールは一向に片づかなかった。仕事が忙しくて時間が取れなかったのだ。まあ、一番悪いのは私の怠惰なのだが。
ある夜、散らかった部屋で原稿を書いていると、インターフォンが一度鳴った。
階下のオートロックドアの呼び出しならば、「ポーン、ポーン」と二度続けて鳴る仕組みになっている。一度しか鳴らないのは、この部屋のドアの外についているインターフォンが直接鳴らされたしるしだった。
念のため、「どちら様?」と聞いてみると、甲高い女性の声が返ってきた。
「こんばんわぁ。二○四号室の吉村といいます」
私はドアを開けてみた。小柄なショートカットの女性が立っていた。年齢は私と同じか、少し若いぐらいだろう。
吉村と名乗った女性は、上目遣いに私を見て笑った。前歯が出ているせいか、ねずみっぽい顔つきだ。
「すみません、急にお邪魔して」
「いえ」
「今ね、ちょっと、下で騒ぎになってるんですよ。それで、寺内さんにもお知らせしたほうがいいと思って」
この人に名前を名乗った覚えはないので、いきなり苗字で呼びかけられて面食らった。まあ、階下の郵便受けに表札を出してあるから、名前を知られているのも不思議ではないのだが。吉村さんの言い方には、なんとなく不快ななれなれしさが感じられた。
「騒ぎって、何ですか」
「変な臭いがするんですよ。一階の、入り口のところ」
「臭い?」
「ええ。消毒液みたいな。ちょっと、下りてきてもらえませんか」
吉村さんは私の返事も待たずに背を向けて歩き出した。
野末さんは話好きらしく、まだいろいれら語りたそうだったが、私は適当に切り上げた。引っ越し早々、住人のトラブルに巻き込まれたくはない。
最上階の林原さんには要注意、と心のメモに書き留めておくことにした。
☆
一週間経っても、部屋の中のダンボールは一向に片づかなかった。仕事が忙しくて時間が取れなかったのだ。まあ、一番悪いのは私の怠惰なのだが。
ある夜、散らかった部屋で原稿を書いていると、インターフォンが一度鳴った。
階下のオートロックドアの呼び出しならば、「ポーン、ポーン」と二度続けて鳴る仕組みになっている。一度しか鳴らないのは、この部屋のドアの外についているインターフォンが直接鳴らされたしるしだった。
念のため、「どちら様?」と聞いてみると、甲高い女性の声が返ってきた。
「こんばんわぁ。二○四号室の吉村といいます」
私はドアを開けてみた。小柄なショートカットの女性が立っていた。年齢は私と同じか、少し若いぐらいだろう。
吉村と名乗った女性は、上目遣いに私を見て笑った。前歯が出ているせいか、ねずみっぽい顔つきだ。
「すみません、急にお邪魔して」
「いえ」
「今ね、ちょっと、下で騒ぎになってるんですよ。それで、寺内さんにもお知らせしたほうがいいと思って」
この人に名前を名乗った覚えはないので、いきなり苗字で呼びかけられて面食らった。まあ、階下の郵便受けに表札を出してあるから、名前を知られているのも不思議ではないのだが。吉村さんの言い方には、なんとなく不快ななれなれしさが感じられた。
「騒ぎって、何ですか」
「変な臭いがするんですよ。一階の、入り口のところ」
「臭い?」
「ええ。消毒液みたいな。ちょっと、下りてきてもらえませんか」
吉村さんは私の返事も待たずに背を向けて歩き出した。
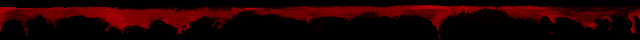
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える