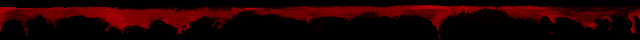
庭師-ブラック・ガーデナー-
第2章 1
「ご近所には挨拶に行ったの?」
「うん。みんないい人たちみたい」
三つめの嘘。引っ越し挨拶は、面倒なので省略するつもりだった。近所付き合いする気はないし、エレベーターなどで顔を合わせた時に挨拶しておけば十分だろう。
しかし、母のような気性の人にそんなことを言ったら、「だらしがない」「常識がない」と叱られるに決まっているので、適当に調子のいいことを言っておいた。
母は、近くに病院はあるのかとか、最寄りの交番に一度挨拶しておくといいとか、新聞の勧誘には気をつけろとか、細かい注意をいろいろ並べ、最後に取ってつけたように「ローンが大変でしょう。がんばらなくちゃね」と言った。
がんばらなくちゃ。その言葉は、私にはちょっとばかり苦痛だった。私は適当に会話を切り上げ、受話器をそっと置いた。
台所に引き返し、紅茶を淹れたカップを手に、床に座りこむ。一応、リビングにはテーブルがあるのだが、私は椅子よりも床にぺたっと座るほうが好きだ。座ったまま摺るように移動する私を見て、浩一はよく「また床を掃除してる」と笑ったものだ。
カップを両手で持って、熱い液体を胃に流しこむ。ほっとした。けれども、いよいよ自分のお城で新しい生活を始めるのだという高揚感は全然感じられなかった。むしろ、疲労と不安がどっとあふれ出てきて、私はため息をついた。
なぜか涙が出てきた。片手で目をこすりながら紅茶をすすった。
悲しいわけではないのに。自律神経失調気味だ。
引っ越し業者の青年たちは、運んでも運んでも終わらない夥しいダンボール箱に、さすがにうんざりした様子だった。箱につけたラベルには、全部「本」と書かれている。重いのだ。
「すごい量ですね。出版社にお勤めなんですか?」
業者チームのリーダーっぽい人からそう聞かれた。私は適当に笑って「はあ、まあ」と答えておいた。
本当は「お勤め」なんてしてない。しがないフリーライターだ。だが、この職業を他人に説明するのはちょっと面倒くさい。出版界に縁のない人には、フリーライターなんて何をするものだかよくわからないらしいのだ。
「うん。みんないい人たちみたい」
三つめの嘘。引っ越し挨拶は、面倒なので省略するつもりだった。近所付き合いする気はないし、エレベーターなどで顔を合わせた時に挨拶しておけば十分だろう。
しかし、母のような気性の人にそんなことを言ったら、「だらしがない」「常識がない」と叱られるに決まっているので、適当に調子のいいことを言っておいた。
母は、近くに病院はあるのかとか、最寄りの交番に一度挨拶しておくといいとか、新聞の勧誘には気をつけろとか、細かい注意をいろいろ並べ、最後に取ってつけたように「ローンが大変でしょう。がんばらなくちゃね」と言った。
がんばらなくちゃ。その言葉は、私にはちょっとばかり苦痛だった。私は適当に会話を切り上げ、受話器をそっと置いた。
台所に引き返し、紅茶を淹れたカップを手に、床に座りこむ。一応、リビングにはテーブルがあるのだが、私は椅子よりも床にぺたっと座るほうが好きだ。座ったまま摺るように移動する私を見て、浩一はよく「また床を掃除してる」と笑ったものだ。
カップを両手で持って、熱い液体を胃に流しこむ。ほっとした。けれども、いよいよ自分のお城で新しい生活を始めるのだという高揚感は全然感じられなかった。むしろ、疲労と不安がどっとあふれ出てきて、私はため息をついた。
なぜか涙が出てきた。片手で目をこすりながら紅茶をすすった。
悲しいわけではないのに。自律神経失調気味だ。
引っ越し業者の青年たちは、運んでも運んでも終わらない夥しいダンボール箱に、さすがにうんざりした様子だった。箱につけたラベルには、全部「本」と書かれている。重いのだ。
「すごい量ですね。出版社にお勤めなんですか?」
業者チームのリーダーっぽい人からそう聞かれた。私は適当に笑って「はあ、まあ」と答えておいた。
本当は「お勤め」なんてしてない。しがないフリーライターだ。だが、この職業を他人に説明するのはちょっと面倒くさい。出版界に縁のない人には、フリーライターなんて何をするものだかよくわからないらしいのだ。
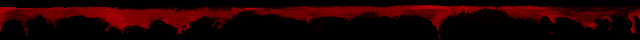
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える