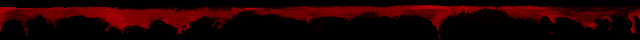
庭師-ブラック・ガーデナー-
第2章 1
要するに私にも「○○先生を出せ」の電波学生とあまり違わなかったのかもしれない。
でも好きでやってるんだと自分に言い聞かせるのにも限界があった。文章を書いてお金をもらえることに喜びを感じられたのは、最初の数か月だけ。くる日もくる日もルーティン・ワークをこなし続けるうちに、どんどん自分が擦り切れていくような気がした。自分が何をしたいのか、どんなものを書きたいのかわからないまま、気がついたら二十九歳になっていた。
編集者にとっては若いライターのほうが使いやすいし、得意分野のない何でも屋なんて、使い捨てだ。いずれは切り捨てられる。焦燥感から、浩一に愚痴ることがめっきり増えた。
浩一は大学の同級生で、学生時代から付き合い続けている相手だった。美形というほどではないがまあまあ整った顔立ちで、背も高い。性格は優しくて、少々頼りない。お父さんもお兄さんも公務員で、本人も当たり前のように公務員になった。面白みのある性格ではないが、相槌の打ち方が絶妙で、話の間合いがちょうどいい。一緒にいて楽、というのが長く付き合ってこられた理由だった。
私の愚痴を、浩一はいつも優しく聞いてくれた。下手になだめたり同情したりせず、黙って愚痴らせてくれるので、私は彼の前では安心して毒づくことができた。
一度だけ、私の愚痴が原因で喧嘩になったことがある。愚痴が原因というより、浩一が冗談めかして「そんなに仕事イヤなら、お嫁さんになっちゃいなよ」と茶化したのが原因だった。
浩一の性格からして、冗談めかした本音のプロポーズだったんだろうと思う。それがわかるだけに、私はムッとした。ぷっと膨れて、浩一から顔を背けた。浩一は(たぶん、私が何に怒っているのかわからないまま)戸惑い顔で謝った。
結婚なんて、考えたくなかった。それは、私の望んでいる未来ではなかった。浩一のことは好きだったし、いずれは一緒になるんだろうなと思っていたけれど、その前に私は何か形になる仕事をしておきたかった。
原稿を書いていても、いつまでこんなことを続けるんだという焦りが始終付きまとっていた。成功している他人がうらやましく、ねたましかった。
でも好きでやってるんだと自分に言い聞かせるのにも限界があった。文章を書いてお金をもらえることに喜びを感じられたのは、最初の数か月だけ。くる日もくる日もルーティン・ワークをこなし続けるうちに、どんどん自分が擦り切れていくような気がした。自分が何をしたいのか、どんなものを書きたいのかわからないまま、気がついたら二十九歳になっていた。
編集者にとっては若いライターのほうが使いやすいし、得意分野のない何でも屋なんて、使い捨てだ。いずれは切り捨てられる。焦燥感から、浩一に愚痴ることがめっきり増えた。
浩一は大学の同級生で、学生時代から付き合い続けている相手だった。美形というほどではないがまあまあ整った顔立ちで、背も高い。性格は優しくて、少々頼りない。お父さんもお兄さんも公務員で、本人も当たり前のように公務員になった。面白みのある性格ではないが、相槌の打ち方が絶妙で、話の間合いがちょうどいい。一緒にいて楽、というのが長く付き合ってこられた理由だった。
私の愚痴を、浩一はいつも優しく聞いてくれた。下手になだめたり同情したりせず、黙って愚痴らせてくれるので、私は彼の前では安心して毒づくことができた。
一度だけ、私の愚痴が原因で喧嘩になったことがある。愚痴が原因というより、浩一が冗談めかして「そんなに仕事イヤなら、お嫁さんになっちゃいなよ」と茶化したのが原因だった。
浩一の性格からして、冗談めかした本音のプロポーズだったんだろうと思う。それがわかるだけに、私はムッとした。ぷっと膨れて、浩一から顔を背けた。浩一は(たぶん、私が何に怒っているのかわからないまま)戸惑い顔で謝った。
結婚なんて、考えたくなかった。それは、私の望んでいる未来ではなかった。浩一のことは好きだったし、いずれは一緒になるんだろうなと思っていたけれど、その前に私は何か形になる仕事をしておきたかった。
原稿を書いていても、いつまでこんなことを続けるんだという焦りが始終付きまとっていた。成功している他人がうらやましく、ねたましかった。
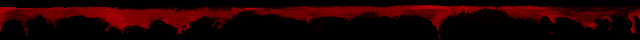
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える