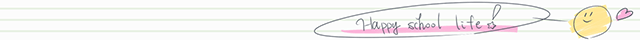
その恋を残して
第7章 眠り姫……か
言ってしまってから、とても焦った。
どうして、そんなこと口走ってしまったのか。反応が怖くて、おそるおそる母さんの顔を見ると――
キョトンと俺を眺めていたその顔が、直後に――
「プッ! フフフ――アハハハ!」
思い切り吹き出すと、笑い始めた。
顔が真っ赤に紅潮してゆくのが、自分でもわかった。
「わ……笑うなって!」
「ウフフ……ゴメンゴメン。なんだぁ、そうかそうか」
「……?」
妙に納得した母さんの態度を、俺は不思議に眺める。
「悩んでるくらいなら、さっさと会いに行きなさいよ。恋しい彼女に」
「な、なにも知らないくせに、勝手なこと言うなよ」
「知ってるわよ」
母さんは、あっけらかんとして言った。
「知ってるって……なにを?」
そう訊くと、母さんはこんな風に答えている。
「宋史が優しい子だってことを――母さんはね、誰よりもよく知ってるの」
「ばっ――」
馬鹿なこと言うなって――そう言おうとして、思わず言葉が詰まった。不思議なくらい胸が熱くなって、不意に涙が零れそうになった。
「臆病で慎重――だけど、その内に秘めているものは純粋な優しさ。その点では自慢の息子だわ。そんなアンタが恋した相手なら、間違いないって思う。その娘がいい娘だってことも、母さんわかってるから」
「……」
「そりゃ、さ。なにがあったのか詳しくは知らない。でもね、アンタが本気なのは伝わってるよ。だったら、たぶん。今、足りないものは――ほんの少しの勇気なんじゃない?」
勇気――そんな言葉は、至る所で散々聞かされて聞き飽きたような言葉。まるで綺麗事の象徴のように感じていたその言葉が――けれど、この瞬間に、俺の心に響き渡った。
「ホント、勝手な言い草だ」
「なによ」
「母さん――出かけてくるね」
俺がそう告げると、母さんはニッコリと笑った。
「すぐにご飯作るから、シャワーでも浴びてなさい。出かけるのは、それからでいいでしょう」
「うん――」
微笑み、頷く。
どうして、そんなこと口走ってしまったのか。反応が怖くて、おそるおそる母さんの顔を見ると――
キョトンと俺を眺めていたその顔が、直後に――
「プッ! フフフ――アハハハ!」
思い切り吹き出すと、笑い始めた。
顔が真っ赤に紅潮してゆくのが、自分でもわかった。
「わ……笑うなって!」
「ウフフ……ゴメンゴメン。なんだぁ、そうかそうか」
「……?」
妙に納得した母さんの態度を、俺は不思議に眺める。
「悩んでるくらいなら、さっさと会いに行きなさいよ。恋しい彼女に」
「な、なにも知らないくせに、勝手なこと言うなよ」
「知ってるわよ」
母さんは、あっけらかんとして言った。
「知ってるって……なにを?」
そう訊くと、母さんはこんな風に答えている。
「宋史が優しい子だってことを――母さんはね、誰よりもよく知ってるの」
「ばっ――」
馬鹿なこと言うなって――そう言おうとして、思わず言葉が詰まった。不思議なくらい胸が熱くなって、不意に涙が零れそうになった。
「臆病で慎重――だけど、その内に秘めているものは純粋な優しさ。その点では自慢の息子だわ。そんなアンタが恋した相手なら、間違いないって思う。その娘がいい娘だってことも、母さんわかってるから」
「……」
「そりゃ、さ。なにがあったのか詳しくは知らない。でもね、アンタが本気なのは伝わってるよ。だったら、たぶん。今、足りないものは――ほんの少しの勇気なんじゃない?」
勇気――そんな言葉は、至る所で散々聞かされて聞き飽きたような言葉。まるで綺麗事の象徴のように感じていたその言葉が――けれど、この瞬間に、俺の心に響き渡った。
「ホント、勝手な言い草だ」
「なによ」
「母さん――出かけてくるね」
俺がそう告げると、母さんはニッコリと笑った。
「すぐにご飯作るから、シャワーでも浴びてなさい。出かけるのは、それからでいいでしょう」
「うん――」
微笑み、頷く。
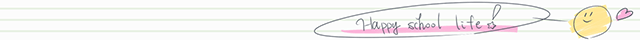
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える