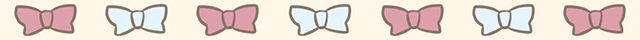
女子高生香織の痴漢列車
第3章 囚われの
(この変態が……)
そう思いながらも、香織はほっと胸を撫で下ろしていた。もちろん他人に見られながら自慰行為をするなど消えてしまいたいほど恥ずかしい。だが、その精神的な恥ずかしささえ無視すれば自室でする場合と変わらなかった。
盗撮をするような外道ならば、もっとキスさせろだとか胸を揉ませろだとかというムチャな要求をされかねないと思っていたのだ。
「は、始めますね」
羞恥心に顔が熱くなるのを感じながら、香織は座ったまま股の間に手を伸ばす。
「いやいやいや、違うなぁ。あの時のようにやってくれよ。最後までいかなきゃ終わらないよ?」
あの時というのが、トイレで香織が盗撮された時のことを指しているのは明白だった。香織はのろのろと足をソファに上げる。スカートがめくれ、薄い桜色の下着と、そこから伸びる雪のような白さの太ももが露わになった。恒がごくりと生唾を飲み込む音が聞こえる。
香織はゆっくりと手を伸ばし、敏感な割れ目まで持っていくと、中指でそっとなぞった。
「……?」
しかし何も感じない。いつもならじんわりとした快感を生むはずだったのだが、今は前腕を撫でられたように、ただ触れたという感触があっただけだった。
そのまま10分弱の間、香織は自分を刺激し続けた。どれだけ撫でてもいつものように気持ちよくなることはなく、念のために下着の中へ指を入れて直接触ってみるも、こちらはいつも通り全く濡れていなかった。
いつまで経っても香織がそのようなことを繰り返しているのを見て焦れたのだろうか。ついに恒は立ち上がると言った。
「いつまでそんなことをしているんだ。早くパンツを脱げ」
やっぱりこのまま終わらせるのはダメか。香織は落胆しながら、
「無理ですよ……」
「どうして」
「濡れてないから直接触っても痛いだけなんです」
「どうしても無理なのか?」
「はい」
香織がそう答えると、恒は「よし、わかった」と言って立ち上がった。香織のソファの近くまで歩いてくると、
「もう手を止めていいよ」
と言う。
「あ、はい。わかりました」
流れが理解できずキョトンとする香織に、
「じゃあ両腕を上に上げて」
恒はそう指示を出した。
そう思いながらも、香織はほっと胸を撫で下ろしていた。もちろん他人に見られながら自慰行為をするなど消えてしまいたいほど恥ずかしい。だが、その精神的な恥ずかしささえ無視すれば自室でする場合と変わらなかった。
盗撮をするような外道ならば、もっとキスさせろだとか胸を揉ませろだとかというムチャな要求をされかねないと思っていたのだ。
「は、始めますね」
羞恥心に顔が熱くなるのを感じながら、香織は座ったまま股の間に手を伸ばす。
「いやいやいや、違うなぁ。あの時のようにやってくれよ。最後までいかなきゃ終わらないよ?」
あの時というのが、トイレで香織が盗撮された時のことを指しているのは明白だった。香織はのろのろと足をソファに上げる。スカートがめくれ、薄い桜色の下着と、そこから伸びる雪のような白さの太ももが露わになった。恒がごくりと生唾を飲み込む音が聞こえる。
香織はゆっくりと手を伸ばし、敏感な割れ目まで持っていくと、中指でそっとなぞった。
「……?」
しかし何も感じない。いつもならじんわりとした快感を生むはずだったのだが、今は前腕を撫でられたように、ただ触れたという感触があっただけだった。
そのまま10分弱の間、香織は自分を刺激し続けた。どれだけ撫でてもいつものように気持ちよくなることはなく、念のために下着の中へ指を入れて直接触ってみるも、こちらはいつも通り全く濡れていなかった。
いつまで経っても香織がそのようなことを繰り返しているのを見て焦れたのだろうか。ついに恒は立ち上がると言った。
「いつまでそんなことをしているんだ。早くパンツを脱げ」
やっぱりこのまま終わらせるのはダメか。香織は落胆しながら、
「無理ですよ……」
「どうして」
「濡れてないから直接触っても痛いだけなんです」
「どうしても無理なのか?」
「はい」
香織がそう答えると、恒は「よし、わかった」と言って立ち上がった。香織のソファの近くまで歩いてくると、
「もう手を止めていいよ」
と言う。
「あ、はい。わかりました」
流れが理解できずキョトンとする香織に、
「じゃあ両腕を上に上げて」
恒はそう指示を出した。
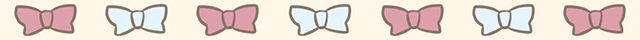
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える